今回は、「自分とか、ないから。教養としての東洋哲学」という本について紹介させて頂きながら、東洋哲学について論じていきたいと思います。この本は「しんめいp」さんという東洋哲学に精通していない人が、32歳の時に無職になり離婚して、引きこもりになって末の虚無感がきっかけになっています。西洋哲学を読んで、ニーチェの虚無感に関する「ツァラトゥストラはかく語りき」という本も読んで、最後に発狂して亡くなったことを知って、ある日、東洋哲学を知った。その中で、おもしろいのは表情を比べたんですね。デカルト、ニーチェ、ヘーゲルとみんな虚無感を抱えているような顔しているのに、ブッダはやすらかそうな顔をしていることに着目している。すごい基本的でするどい視点を持っていますね。そしてだんだんと東洋哲学を学び、面白おかしく、そしてうまくまとめられていて、それも肝心要な点をはずしていません。ですのでちょっと本を読むと初心者向けですし、とっつきやすい反面、書きっぷりに賛否両論分かれそうですが、私は面白いと思ったので、この著書を紹介させて頂きながら私なりの感想をまとめていきたいなと思います。
なお今回は、その中でもブッダと龍樹についてまとめています。
それでははじめていきます。
1.無我 自分なんてない ブッダの哲学
ブッダについてうまくまとめていますね。出家をホームレスになることっていいながら、ある日家出して、そのまま一生外に出てしまったと書いていますね。著書はブッダの虚無感が強調されていますが、実際には生老病死の姿、つまり苦しみの姿をみて、出家したとされていますね。おそらく虚無感を強調していたのは、著者自身の虚無感を何とかしたい重いからではないかと思います。それはさておき、インドは2500年前から自分探しの本場として表現されています。そして「めっちゃ身体をいためつけたら、本当の自分があらわれる」という風潮があったらしい」という表現で、ブッダが苦行をしたことが書かれています。実際に、今でもずっと片足で過ごす人や腕を上げ続けている人、火の中に入る人など、インドは苦行によりカルマを浄化し、来世を見据えた人生を送っている人が多くいますね。自分を探しているのかどうかはわかりませんが、真理を知りたいという思いや解脱を成し遂げたいという思いが強いことは明らかですね。話を戻すとブッダもそんな苦行の末に、苦行ではないことを知りやせこけた体に対して差し出されたスジャータの乳粥を食べて体力を回復して、菩提樹の木の下で瞑想をして、悟りを開いたとされていますね。この著書では、この悟りの境地を本のタイトルの通り「自分とか、ない」と表現しました。いわゆる無我のこととしています。うまい表現ですね。キャッチ―な表現になってます。自分というものはない、自分とはただの妄想という事で、これを著者は面白い表現で例みしています「自分の身体は、食べ物、つまり自分以外の物からできているのだ」と表現しています。このきっかけを含めて全てのつながりを表現しています。さらに「息」や「オナラ」ですら循環しているといっています。確かにという感じで、すごく世間的にうまくリアリティを突き付けていますね。次に「カレー食べたい」という思考は、どこからともなく勝手に湧き上がってきたことにホラーと表現しています。これはいわゆる自動思考ですね。ずっと生まれてこの方、自分で思考していると思っていたものが揺らいだ時の表現としては、かなりベストな表現だと思います。そして苦しみの原因は「自分」なのだとまとめています。全てが変わっていくこの世界で、変わらない「自分」をつくろうとしているとも言っています。これは、ブッダのもう一つの真理である無常を追加していますね。無常については、著書では書かれていませんが、表現されています。ここまでの章でいうと実は、虚無感の解放を感じないように思います。ブッダの思想自体は虚無感には襲われない境地に至っていると思いますが、この内容だけですと全くそのように捉えられないですね。おそらく著者は次の龍樹の哲学で、本質の虚無感の解放に向かって著書を作成していると思います。
2.空 この世はフィクション 龍樹の哲学
龍樹というのは、2~3世紀ごろの仏教哲学者で、大乗仏教の空を体系的に論じた天才ですね。ブッダの思想をわずか1文字にしたと著書では書かれていますね。これが空です。ここで龍樹の言葉が引用されています
「この世のすべては、ただ心のみであって、あたかも幻のすがたのように存在している。」
著書は幻という表現というより「この世界はすべて「フィクション」である。と言い直していますね。
またもう一つ紹介しています。
「この世界はことばの虚構から生じている」
著者は、これをこの世界は、「ことばの魔法」がうみだした幻なのだと言っています。
そしておじさんの写真に言葉を入れて、社長、CIA、クリエイティブディレクターなどと入れて、イメージが変わることをうまく示しています。同様にファミチキを紹介して、これをファミチキではなく「鳥の死体」と表現したらとしています。
ここで大事なのは、言葉ですね。言葉という概念を付着させることによって、様々な印象を操作していますね。より幻に拍車がかかっているわけです。このようにより魔法をかける手段に言葉というのはありますね。希望もそうですし、パッケージもそうですし、あらゆるデザインが付着することによって、全てはイメージが変わってくる。幻影に囚われているわけですね。これを所謂マーケティングや広告戦略として、意図して活用しているわけですね。ユーチューブのサムネイルもそうですね。より魅力的に、実際の内容ではなく、印象を操作しているわけです。
またモノについてもうまく表現しています。
土がコップになったりする。ゴミにもなる。ビルも幻、コンクリートでできている。要するに土。突き詰めて言うと原始時代から土を使った考え方は変わっていない。これらは縁起によって繋がっているとしたわけですね。幻だからなくなれば無ではなく、縁起によってつながっているとしたわけですね。
さらに著者はもっとわかりやすい表現で
水をのむってことは、
「雲」が「自分」になるってことと表現しています。
「雨」が「自分」になるってこと。
「山」が「自分」になるってこと。
「川」が「自分」になるってこと
こうなると世界の見え方がかわると言っています。
エモいねと表現していますね。このような形で表現しながら最終的に龍樹の後進の人の「一によって全てを見る」という表現をもって、米粒に宇宙を見る人の世界に空はなると言っています。
このように幻と言いながら全てがつながっている空の世界には、どことなく縁起という分け隔てのない無境界な世界が広がっていますね。この無ではなく空の世界だからこそ、虚無感という暗闇に突き落とすことは無く、世界や宇宙を軽やかに自由に感じることが出来るのだと思います。空の世界は縁起の世界によって、どこにもとどまることなくとらわれることなく豊かな世界が広がっています。そういった意味で、龍樹の存在はとても大きかったですし、大乗仏教の理論的基盤を築くきっかけにもなっていますので、まさに天才と言える方でしたね。
■引用参考文献『自分とか、ないから。教養としての東洋哲学』サンクチュアリ出版 しんめいP著

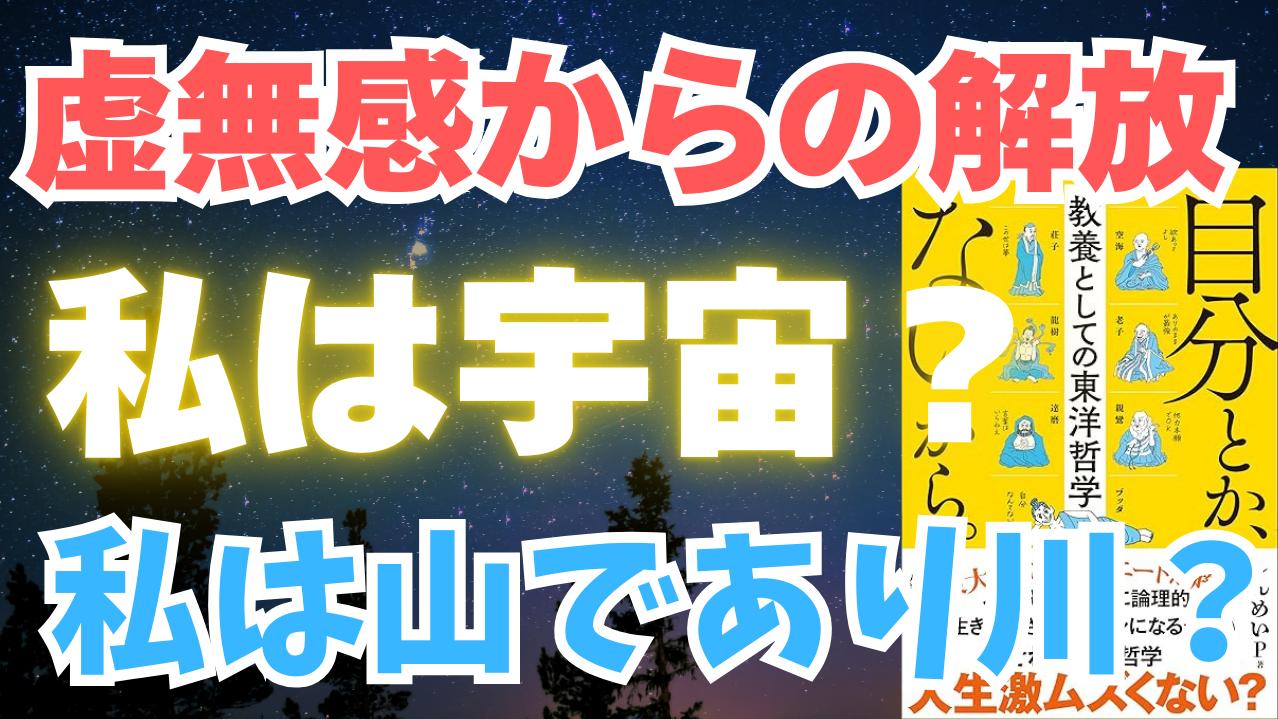
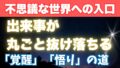

コメント